-
2/14
今日聴いたコンサート@ルドルフィヌム ドヴォルザーク・ホール
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会
(EFチクルス第5回 / 第1日)指揮:サー・ジョン・エリオット・ガーディナー
ヴァイオリン:ヴィクトリア・ムローヴァベートーヴェン:バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43 序曲
プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 作品63
ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
私が大学2年生だった時に発売された、ガーディナー氏とオルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティークによるベートーヴェン交響曲全集のCDは、私が最も影響を受けた録音の1つです。当時はまだベーレンライター版も出版されていなかった頃。斬新な解釈、速いテンポ、硬質な響きから立ちのぼる「ベートーヴェンはこうでなくてはならない!」と言わんばかりの意思の強さ。私はすっかり感化されてしまい、自分なりに自筆譜のファクシミリにあたってみたり (しかし、あまりの判読不能な筆跡に挫折・・・) 、速いテンポを設定したりして、ちょうど振りはじめたいくつかのアマチュアのオーケストラにぶつけてみたりしていました。あまりにそのやり方が行き過ぎたので、数年後、浅い知識と考えでそのようなことはするべきではないと、あえて自らその方向を避けるようになったほど。
そんな学生時代の「神」ともいえる存在が、チェコ・フィルにいらっしゃいました。しかも、高校生の時からのファンであるムローヴァさんまで。
先週・先々週は小林研一郎氏のもとで特濃の響きを奏でていたチェコ・フィルですが、今日は全くそれが夢であったかのような、まるで古楽器のオーケストラかと思うような引き締まった響きを奏でました。ちなみに弦楽器は12型 (いつもは14型) の対向配置 (チェロ・バスは下手) でしたが、ナチュラル・ホルンやナチュラル・トランペット、バロック・ティンパニを用いたりすることは一切ありませんでした。弦楽器のヴィブラートに関しては、確かにノン・ヴィブラートにしていた箇所は多くはありましたが、逆に言えばはいつも通りのヴィブラートを用いていたように見受けられた箇所も少なくありませんでした。ここらへんは、モダン・オーケストラを指揮される際のガーディナー氏のスタンスといったところなのでしょうか。
「プロメテウス」の第一音からびっくりするような鋭い響きでした。チェコ・フィルにはノイマン氏とのこの曲のレコーディングがありますが、たぶんその録音の16分の1くらいの長さではないかと・・・ ものすごいスーパー・スタッカートでした! それから主部の速さといったら尋常ではありませんでした。それだけではなくて、細かい音符にも語るような表情があったのにはただ感嘆するのみ。ちなみに演奏会が終わって部屋に戻ってきてから、ジンマン・ノリントン・ハーディングその他各氏の録音を聴き直してみましたが、今夜のガーディナー氏の速さに比べると眠くなるようなテンポに感じました。恐る恐る自分が演奏した時の録音も聴いてみましたが、まるで時が止まるように感じられました・・・ もちろん速ければ良いというものではありませんが、何が言いたいかというと、そのくらい衝撃的な演奏だったということです。
残りの2曲のことはまた明日書いてみたいと思います。
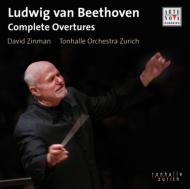 今日のBGM: ベートーヴェン:序曲全集
今日のBGM: ベートーヴェン:序曲全集
デイヴィッド・ジンマン指揮チューリヒ・トーンハレ管弦楽団
(2004年録音、Arte Nova)






